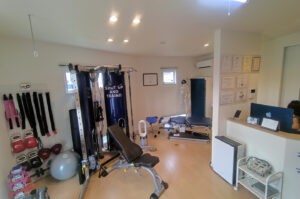カイゼン先生の健康教室 - 血流制限トレーニングの秘密
カイゼン先生は、KAIZEN TRIGGERの診療室で、いつものように丁寧にカルテを整理していました。その日は雨が降っていて、窓から見える牛久市の景色もしっとりと落ち着いた雰囲気に包まれていました。
「カイゼン先生、ちょっとよろしいですか?」と、受付のトリ子さんが診療室のドアをノックしました。
「どうぞ、トリ子さん。何かあったかな?」カイゼン先生は穏やかな表情で答えました。
「実は、先日新しく入会された佐藤さんからの質問なんですが、血流制限トレーニングについて詳しく知りたいとのことでした。私もカイロプラクティック整体とパーソナルトレーニングを組み合わせた当院の特徴である血流制限トレーニングのことをもっと理解したいと思いまして...」トリ子さんは少し恥ずかしそうに言いました。
「なるほど。確かに血流制限トレーニングは最近注目されていますね。当院でも多くの患者さんに効果を実感していただいています。少し時間をとって説明しましょうか?」
「ありがとうございます!実は私自身、先日膝を痛めてしまって、リハビリの必要があるんです。血流制限トレーニングが役立つかもと思って...」
カイゼン先生は眼鏡を直し、「それは良いタイミングですね。血流制限トレーニング、略してBFRは、特に怪我からの回復期に効果的なんですよ。」と話し始めました。
「BFRとは具体的にどういうものなんですか?」トリ子さんは熱心にメモを取りながら尋ねました。
「簡単に言うと、トレーニング中に専用のバンドやカフを使って血流を部分的に制限することで、軽い負荷でも高強度トレーニングと同等の効果を得る方法です。これは術後のリハビリや怪我からの回復において非常に価値があるんですよ。」
「へぇ、軽い負荷で効果があるなんて素晴らしいですね!でも血液の流れを制限するって少し怖いような...」トリ子さんは少し不安そうな表情を見せました。
「その心配はよく聞かれますね。確かに適切な知識と機器がなければ危険です。ですが、私たちKAIZEN TRIGGERでは、専門的なトレーニングを受けたスタッフが最新の研究に基づいて安全に実施しています。血流は完全に遮断するのではなく、動脈の血流を減少させながら静脈の流れを制限するという精密な調整が必要なんです。」
「なるほど...それで、どんな効果があるんですか?」
「主な効果は筋肥大と筋力向上ですが、それだけではないんですよ。実は心肺機能の向上や痛みの軽減、さらには骨密度の改善にも役立つという研究結果があります。特に興味深いのは、通常の20~40%の軽い負荷でも、高負荷トレーニングと同等の効果が得られることです。」
カイゼン先生はホワイトボードに簡単な図を描きながら続けました。「例えば、膝を痛めた場合、通常のリハビリでは痛みを避けるために負荷を下げざるを得ませんが、それでは筋肉の減少を防ぎきれません。BFRを使えば、関節への負担を最小限に抑えながら、効果的に筋肉の維持や回復ができるんです。」
「わぁ、それは私のような状況にぴったりですね!」トリ子さんは目を輝かせました。「実際にどのように行うんですか?」
「まず専用の圧力計付きカフを腕や脚の付け根近くに装着します。そして個人の血流を測定して、最適な圧力を設定します。これは人によって異なるので、専門家の判断が必要です。その後、軽い負荷でのエクササイズを行います。」
「なるほど...でも、どんな人にも適しているんですか?」
「良い質問ですね。基本的には多くの方に有効ですが、深部静脈血栓症の既往がある方や重度の高血圧、心臓疾患がある方など、いくつか注意が必要なケースもあります。だからこそ、私たちのようなプロフェッショナルの指導のもとで行うことが重要なんです。」
トリ子さんは膝を触りながら考え込みました。「先生、私の膝の状態でも始められますか?」
「今の状態を詳しく診て判断する必要がありますが、適切な設定であれば、むしろ回復を早める可能性が高いですよ。今日の診療が終わったら、詳しく診察しましょうか?」
「ぜひお願いします!」トリ子さんは嬉しそうに立ち上がりました。「患者さんにも自信を持って説明できそうです。みなさんにもこの素晴らしいトレーニング方法を知ってもらいたいです!」
「その前に、あなた自身が体験することが一番の理解につながりますよ。」カイゼン先生は微笑みました。
その日の夕方、カイゼン先生の指導のもと、初めての血流制限トレーニングに挑戦したトリ子さん。翌朝、「先生!信じられないくらい効いた感じがします!筋肉が活性化したような...」と報告に来ました。
「それこそがBFRの魅力ですね。低負荷でも高強度トレーニングと同等の効果を感じられる。特に膝のようなデリケートな部位のリハビリには最適なんです。」
「カイゼン先生、これからも牛久市の皆さんに、この素晴らしいトレーニング方法と、私たちKAIZEN TRIGGERのカイロプラクティック整体とパーソナルトレーニングの組み合わせの価値を伝えていきたいです!」トリ子さんはきらきらした目で宣言しました。
カイゼン先生は満足そうにうなずきました。「それが私たちの使命ですね。健康改善のトリガーになること。さぁ、今日も一緒に頑張りましょう。」
血流制限トレーニング(BFR)の科学と実践:スポーツリハビリとパフォーマンス向上のための革新的アプローチ
序論:血流制限トレーニングの基礎と可能性
近年、スポーツ医学とリハビリテーションの分野で注目を集めている革新的なアプローチが血流制限トレーニング(Blood Flow Restriction Training: BFR)です。牛久市のKAIZEN TRIGGERでは、カイロプラクティック整体とパーソナルトレーニングを融合させた施設として、この最先端のリハビリテーション手法を取り入れています。BFRは、トレーニングやエクササイズ中に専用のターニケット(止血帯)を使用して動脈の血流を減少させ、静脈の流出を遮断する技術です。当初はこの手法は筋肉の発達を促進する方法として認識されていましたが、その生理学的メカニズムと効果についての理解が深まるにつれ、臨床応用の革新的な可能性が広がっています。
BFRの最も特筆すべき特徴は、関節にかかるストレスを軽減しながらも筋力向上を実現できる点です。特に術後のリハビリテーション、怪我からの回復期、または高負荷トレーニングが制限されている状況下にある方々にとって、BFRは回復を加速し筋萎縮を防止する有効な手段となります。さらに、心血管機能の向上や疼痛緩和にも効果があるという研究結果も増えています。
BFRの歴史を振り返ると、この手法は当初、日本で「KAATSU(加圧)トレーニング」として開発されました。その後、米国で重傷を負った軍人の筋量損失や四肢温存の状況でのリハビリテーションに応用され、注目を集めるようになりました。その後、適用範囲は通常の筋力トレーニング、術後リハビリ、萎縮予防など多岐にわたるようになりました。
現在、BFRの臨床応用は多様化しており、有酸素運動との併用、受動的適用(運動を伴わないBFR)、神経筋電気刺激との組み合わせなど、新たな形態も臨床で適用されています。BFRに関する認知度が高まるにつれ、その生理学的作用メカニズムについての知識も深まり、筋肉の成長以外にも筋持久力、心血管系の健康、疼痛管理、骨密度など多方面での効果が明らかになってきました。
BFRの生理学的メカニズムを理解することは、その実践に先立って重要です。現在の理論では、血管閉塞による代謝ストレスとレジスタンストレーニングや運動による機械的張力が相乗効果を生み出し、筋肥大と筋力向上をもたらすと考えられています。細胞レベルでは、代謝産物の蓄積、ホルモン変化、細胞間シグナル伝達、細胞膨潤、細胞内シグナル伝達経路など多様な機序が関与しています。
特に注目すべきは、BFRによる相対的な虚血および低酸素状態によって増幅される代謝産物の役割です。これらは運動中に蓄積し、筋肥大の既知の媒介物質として、末梢性の疲労を早期に誘導すると考えられています。その結果、より大きな運動単位の動員につながり、通常は高強度でしか優先的に動員されないII型速筋線維が、BFR条件下では低負荷でも活性化されることが示されています。これが、同等の低負荷運動単独と比較して、低負荷BFRでの筋肥大増加の根拠となっています。
興味深いことに、この運動単位の動員の増加は、閉塞部位より遠位の筋肉に限定されません。上肢および下肢のBFRの両方で、より近位の筋群(大殿筋、肩(三角筋/ローテーターカフ)、大胸筋)も対照群と比較してより高いレベルの動員を示すことが証明されています。これは、閉塞部位より遠位の同期筋群の早期疲労に応答して発生すると考えられており、ターニケットを近位に適用できない処置や傷害後のBFR使用において重要な意味を持ちます。
BFRの生理学的効果は、サテライト細胞(筋コネクティブ組織内の多能性細胞で、筋肉の成長と再生を担当)の増殖にも関連しています。当初、サテライト細胞は高負荷抵抗トレーニングの設定でのみ活性化すると考えられていましたが、BFRを伴う低負荷条件下でもその増殖が増加し、筋タンパク質合成、筋核含有量、筋線維サイズ、筋力の増加につながることが明らかになっています。
BFRが示す生理学的適応は、いくつかの注目すべき細胞シグナル伝達経路によっても媒介されています。特に、筋タンパク質合成と肥大に重要なメカニスティックターゲットオブラパマイシン(mTOR)経路を介したタンパク質翻訳の刺激がBFRの効果に根本的な役割を果たしていると考えられます。一方、筋成長の負の調節因子であり筋線維症を促進するマイオスタチンは、BFR後に下方制御されることが示されています。
これらのメカニズムの理解が深まることで、今後のリハビリテーション効果を最適化するための研究がさらに推進されることが期待されます。牛久市のKAIZEN TRIGGERでは、これらの最新の科学的知見に基づき、カイロプラクティック整体とパーソナルトレーニングを組み合わせたアプローチで、効果的な健康改善と身体機能の回復をサポートしています。
本論:血流制限トレーニングの応用と効果的実践
血流制限トレーニング(BFR)は、その適用範囲を従来の筋力トレーニングから大きく広げ、現在ではさまざまな形態が臨床で使用されています。牛久市のKAIZEN TRIGGERでは、このエビデンスに基づいたアプローチをカイロプラクティック整体とパーソナルトレーニングに取り入れ、クライアントの回復と健康増進をサポートしています。
BFRの最も一般的な形態は抵抗運動との併用(BFR-RE)です。複数のシステマティックレビューとメタアナリシスにより、その効果が実証されています。Hughesらによる2017年のシステマティックレビューでは、低負荷BFR-REが単独の低負荷抵抗トレーニングより優れ、筋力と筋サイズの向上において高負荷抵抗トレーニング単独と同等であることが示されました。Lixandrãoらの2018年のメタアナリシスでも、BFRを用いた低負荷トレーニングが筋力と筋肥大において通常の低負荷トレーニングより効果的であることが確認されています。
具体的なBFR-REの推奨プロトコルとしては、1レップマックス(1RM)の20〜40%の負荷と、四肢閉塞圧(LOP)の40〜80%に設定されたBFRカフ圧を組み合わせることが推奨されています。最も一般的に使用される方法は4セット(30回、15回、15回、15回)であり、BFRで見られる有益な適応をもたらします。通常、セット間の休息は30〜60秒が推奨され、より長い期間や間欠的BFR(セット間でカフ圧を解放する)は適応のためのストレスを制限する可能性があります。
BFRセッションは週に2〜3回が推奨され、これは標準的な抵抗トレーニングにおける骨格筋肥大の推奨と一致しています。さらに積極的なレジメンとして、1日2回のBFRトレーニングも、怪我や手術後の早期リハビリ期間に回復を加速するための合理的な選択肢となり得ます。
有酸素運動とBFRの組み合わせ(BFR-AE)の研究は抵抗トレーニングと比較すると限られていますが、絶対的および相対的酸素消費量(VO₂)や疲労までの運動時間を含む有酸素フィットネスの指標が、対照トレーニンググループと比較してより増加することが示されています。興味深いことに、すでに高度にトレーニングされたアスリートでも、BFRと組み合わせた低強度運動でVO₂と筋力に顕著な改善が見られます。
一般的に、有酸素能力を向上させるためには50%VO₂の閾値に達する必要があると考えられていますが、BFR-AEの臨床プロトコルとして、最大VO₂の40%(または約時速3.2〜6.4キロでのウォーキング)を15〜20分間行うだけで、2〜6週間で同様の効果が得られる可能性があります。これらの効果は、静脈還流の減少によって媒介されると考えられており、これは心拍数の増加によって補償され、有酸素適応のための効果的なウィンドウの調整をもたらします。
BFR-AEの主な焦点ではないかもしれませんが、筋力、筋サイズ、グリコーゲン組成、毛細血管繊維密度、そしてタイムドアップアンドゴーや椅子の座り立ちなどの機能的指標の改善も様々な研究で報告されています。
運動を伴わないBFRの効果も注目に値します。術後期間、固定化、ギプス装着または入院中の個人にとって、BFR単独は廃用性萎縮を防ぐための潜在的な解決策となります。非荷重または固定化された個人に関する3つの研究のシステマティックレビューでは、BFRが膝トルクの減少を軽減し、廃用性萎縮を防止することが示されています。
また、昏睡状態のICU患者を対象に、受動的モビライゼーションとBFRを併用し、対側肢を対照として用いた研究では、BFRが太ももの筋萎縮を減少させる効果的な方法であることが示されました。これらの研究では、高い圧力(LOP の70〜100%)が萎縮を防ぐためのより強い刺激を提供し、最も一般的なプロトコルは5分間のBFRの後に3分間の再灌流を行い、これを3〜4サイクル、1日1〜2回、1〜8週間続けるというものです。
KAIZEN TRIGGERでは、これらの科学的知見に基づき、カイロプラクティック整体の理論と技術をBFRと組み合わせることで、より効果的なリハビリテーションを提供しています。特に、脊椎のアライメント調整と神経系の機能最適化を目指すカイロプラクティックアプローチは、BFRの効果を最大化するための土台となります。適切な脊椎機能を維持することで、神経インパルスがより効率的に筋肉に伝達され、BFRトレーニング中の筋肉の反応性が向上する可能性があります。
術後リハビリテーションにおけるBFRの役割も重要です。手術後や固定期間後の萎縮の早期発症と重大な負担は十分に文書化されており、萎縮が回復、総合的機能、および再傷害に及ぼす有害な影響も同様です。固定のみでも、健康な非手術患者は7日間で大腿四頭筋の筋肉が7%減少し、膝手術後の萎縮はそれに比べてより大きく、3週間で最大33%に達します。低負荷(またはノーロード)BFRの利点は、骨格筋の維持の改善、運動後の筋損傷の減少、痛みの軽減、関節への機械的ストレスの軽減により、この集団に理想的です。
BFRは上肢および下肢の手術後の両方で研究されていますが、特に前十字靭帯再建術(ACLR)に大きな関心が払われています。様々な術後プロトコルを用いた複数のランダム化比較試験では、結果にやや差異が見られるものの、手術後の最初の数週間以内に適用される低負荷BFRが、標準的なリハビリテーションよりも筋サイズと筋力の改善に効果的であることが示唆されています。
最近の研究では、膝特異的な患者報告アウトカムの改善、そして標準的なリハビリテーションと比較して膝の痛みと滲出液の減少も示されています。研究の多くは急性の筋肉喪失の軽減に焦点を当てていますが、BFRはより慢性的な術後の不足にも効果を示しています。膝手術後に重度の慢性的な太もも筋力低下を持つ個人の大多数がわずか9回のBFRセッション後に著しい筋力増加を示したという研究もあります。
また興味深いことに、ACLRから平均5年経過し、軽度の持続的な大腿四頭筋欠損を持つ患者でもBFRから恩恵を受けることができたという研究結果もあります。これらの研究のスコーピングレビューでは、ほとんどの研究が筋肉量や筋力の測定値を含んでいるものの、これらの測定値は機能性の評価には限定的な価値しかないことが指摘されています。現行文献の他の注目すべき制限は、伸筋機構から派生した自家移植片(大腿四頭筋腱または膝蓋腱)を使用するACLRにおけるBFRの研究が少ないことです。これは、このシナリオでは大腿四頭筋が萎縮しやすく、BFRの恩恵を増大させる可能性があるため、特に関連性があります。
BFRの安全性に関して、不適切な使用に関連するリスクについて十分な注意が必要です。これは特に、空気圧式ターニケットと較正された圧力よりも精度の低い方法で圧力が適用されるシナリオでの有効性に関する不確実性を考えると重要です。一時的な感覚異常、打撲、遅発性筋肉痛はすべて通常のBFR使用後に生じる可能性がありますが、横紋筋融解症、持続的な痛み、失神発作などの重大な有害事象は、不適切な利用、過度の運動、または中程度または強度の身体活動に十分な健康状態でない個人で発生する可能性があります。
血栓はしばしば初期の研究とBFRの議論でリスクとして挙げられていましたが、血栓塞栓事象のリスクが増加するという証拠はありません。実際、線維素溶解系の刺激を考えると、BFRはそのような事象に対して保護効果を提供する可能性さえあります。
牛久市のKAIZEN TRIGGERでは、カイロプラクティック整体の専門知識とパーソナルトレーニングの技術を組み合わせ、BFRの安全かつ効果的な実施に取り組んでいます。各クライアントの個別のニーズと健康状態を考慮した上で、最適なBFRプロトコルを設計し、リハビリテーションプロセスを最適化しています。
結論:血流制限トレーニングの将来展望と実施ガイドライン
血流制限トレーニング(BFR)は、スポーツ医学とリハビリテーション分野に革命をもたらす可能性を秘めたモダリティとして急速に認知度を高めています。牛久市のKAIZEN TRIGGERでは、カイロプラクティック整体とパーソナルトレーニングを組み合わせたアプローチの中でBFRを活用し、クライアントの回復と健康増進をサポートしています。この革新的な手法は、従来の高負荷トレーニングでは得られない独自の生理学的利点を提供します。
BFRの最も重要な特徴の一つは、代謝ストレスと機械的張力の相乗効果による筋肥大と筋力向上のメカニズムです。Schoenfeld(2010)の研究によると、これらの要素は筋肉の成長において相補的な役割を果たしています。特に注目すべきは、低負荷条件下でもII型速筋線維の活性化が促進される点で、これは通常、高強度トレーニングでのみ達成されるものです。Yasudaら(2009)の研究では、BFR条件下での低負荷筋収縮中の筋活性化の増加が実証されています。
BFRのもう一つの重要な側面は、サテライト細胞増殖の促進です。Nielsenら(2012)の研究では、BFRを伴う低負荷レジスタンストレーニングへの反応として、ヒト骨格筋における筋原性幹細胞の増殖が確認されています。これらの細胞は筋肉の修復と成長に不可欠であり、従来は高強度トレーニングでのみ有意に活性化すると考えられていました。
さらに、BFRは筋タンパク質合成の増加をもたらします。Fujitaら(2007)の研究では、BFR中の低強度レジスタンス運動がS6K1リン酸化と筋タンパク質合成を増加させることが示されています。これらの生化学的変化は、mTOR経路の活性化を通じて媒介され、筋肥大に直接的に貢献します。
臨床応用においては、BFRは術後リハビリテーションに特に有望です。Lambertら(2019)の研究では、前十字靭帯再建術(ACLR)後にBFR療法が全肢の骨と筋肉を保存することが示されています。Hughesら(2019)の研究では、ACLR患者のリハビリテーションにおいて、従来の高負荷抵抗トレーニングと比較してBFRの有効性が実証されています。
牛久市のKAIZEN TRIGGERでは、これらの科学的知見に基づいた実践として、以下の3つの重要なポイントを強調しています:
- 個別化されたアプローチの重要性:BFRプロトコルは個人の特定のニーズ、健康状態、および回復目標に合わせて調整されるべきです。Pattersonら(2019)のガイドラインに従い、KAIZEN TRIGGERでは各クライアントの四肢閉塞圧(LOP)を正確に測定し、適切な圧力設定を確保しています。カイロプラクティック整体の評価と組み合わせることで、脊椎の機能、 神経学的状態、関節の健全性を総合的に評価することで、より効果的なBFRプログラムを設計することが可能になります。
- 安全性と監視の優先: BFRは適切な訓練を受けた専門家の監督下で実施されるべきです。Pattersonら(2019)の研究では、適切な実施ガイドラインに従ったBFRは、標準的な運動モダリティよりも有害事象のリスクを増加させないことが示されています。KAIZEN TRIGGERでは、安全性を最優先し、各セッション中の生理学的反応を慎重に監視しています。特に、心血管系の反応、痛みのレベル、および不快感の兆候に注意を払い、必要に応じてプロトコルを調整します。
- 統合的アプローチの採用: BFRの最大の効果を得るためには、カイロプラクティック整体、栄養サポート、そして適切に設計されたパーソナルトレーニングプログラムを含む包括的なアプローチが不可欠です。Noyes、Barber-Westin、およびSipes(2021)の研究では、慢性的な萎縮性術後大腿四頭筋および腱筋の筋肉において、BFRトレーニングがピークトルク強度を改善できることが示されています。KAIZEN TRIGGERでは、脊椎の機能を最適化し、神経系の効率を高めるカイロプラクティックケアと組み合わせることで、これらの効果をさらに強化することができると考えています。
これらの科学的根拠に基づくアプローチにより、牛久市のKAIZEN TRIGGERは、スポーツ傷害からの回復、術後リハビリテーション、そして全体的な身体パフォーマンスの向上を目指すクライアントに最先端のケアを提供しています。BFRは伝統的なリハビリテーション技術と比較して多くの利点を提供し、特に従来の高強度トレーニングが推奨されないシナリオにおいて価値があります。
BFRの将来の研究方向としては、特定の人口統計学的グループや臨床状態に対する最適なプロトコルの確立、長期的な効果の評価、そして他のリハビリテーション技術との統合方法の検討が含まれます。これらの研究が進むにつれて、BFRの臨床応用はさらに洗練され、より広範な患者層に利益をもたらす可能性があります。
BFRはリハビリテーションと運動医学の分野において革命的なアプローチとなっています。その生理学的メカニズムの理解が深まるにつれ、適用範囲は拡大し続けています。牛久市のKAIZEN TRIGGERでは、この革新的な手法をカイロプラクティック整体とパーソナルトレーニングに統合することで、クライアントの回復と健康増進をサポートしています。私たちの目標は、最新の科学的知見に基づいた個別化されたアプローチを通じて、クライアントが最適な健康状態を達成し維持できるよう支援することです。
BFRの導入を検討している方や、カイロプラクティック整体とパーソナルトレーニングを通じた総合的な健康アプローチに興味がある方は、ぜひKAIZEN TRIGGERにご相談ください。私たちの専門家チームが、あなたの健康目標達成のための最適なプランを設計するお手伝いをいたします。
最後に強調したいのは、BFRの力は単にその生理学的効果だけでなく、個々の状況に合わせて適切に実施されることにあります。専門的な指導と監視の下で行われるBFRは、リハビリテーションの加速、筋力の向上、そして全体的な身体機能の最適化に貢献する強力なツールとなります。KAIZEN TRIGGERでは、この革新的なアプローチを通じて、牛久市とその周辺地域の皆様の健康と幸福をサポートすることに尽力しています。
参考文献:
- Cognetti DJ, Sheean AJ, Owens JG. Blood Flow Restriction Therapy and Its Use for Rehabilitation and Return to Sport: Physiology, Application, and Guidelines for Implementation. Arthroscopy, Sports Medicine, and Rehabilitation. 2022;4(1) .
- Hughes L, Paton B, Rosenblatt B, Gissane C, Patterson SD. Blood flow restriction training in clinical musculoskeletal rehabilitation: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2017;51(13):1003-1011.
- Lixandrão ME, Ugrinowitsch C, Berton R, et al. Magnitude of muscle strength and mass adaptations between high-load resistance training versus low-load resistance training associated with blood-flow restriction: A systematic review and meta-analysis. Sports Med. 2018;48(2):361-378.
- Patterson SD, Hughes L, Warmington S, et al. Blood flow restriction exercise: considerations of methodology, application, and safety. Front Physiol. 2019;10:533.
- Noyes FR, Barber-Westin SD, Sipes L. Blood flow restriction training can improve peak torque strength in chronic atrophic postoperative quadriceps and hamstrings muscles. Arthroscopy. 2021;37(9):2860-2869.
- Lambert B, Hedt CA, Jack RA, et al. Blood flow restriction therapy preserves whole limb bone and muscle following ACL reconstruction. Orthop J Sports Med. 2019;7(3_suppl2):2325967119S00196.
- Yasuda T, Brechue WF, Fujita T, Shirakawa J, Sato Y, Abe T. Muscle activation during low-intensity muscle contractions with restricted blood flow. J Sports Sci. 2009;27(5):479-489.
- Fujita S, Abe T, Drummond MJ, et al. Blood flow restriction during low-intensity resistance exercise increases S6K1 phosphorylation and muscle protein synthesis. J Appl Physiol. 2007;103(3):903-910.